炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルという5大栄養素の基礎知識
- カテゴリー
- 健康の悩み
- ジャンル
- 野菜を食べると健康にいいの?
- 目的(解決できる悩み)
- 食事から摂取する5大栄養素の役割がわかるようになること
- 目次
- 1.食事から摂取する栄養素の基礎知識
- 健康を維持するには食事で5大栄養素をバランスよく食べること
- 2.3大栄養素の役割
- 炭水化物(糖質)
- 炭水化物(食物繊維)
- タンパク質
- 脂質
- 3.ビタミンの役割
- 4.ミネラルの役割
1.食事から摂取する栄養素の基礎知識
食べ物には、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルといわれる5大栄養素があります。
5大栄養素の働きは体を作るのに重要で、バランスよく食事を食べることによって健康な体を維持することができます。
健康を維持するには食事で5大栄養素をバランスよく食べること

人間は体の機能が正常に働くようにする為に、5大栄養素といわれる、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルを体内へ摂取しないと病気になって健康を維持できなくなります。
※人間は、体を動かすエネルギー源、器官や組織を作る材料、体の機能を調節する栄養素が必要不可欠です。
体を動かすエネルギーは、3大栄養素の炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質が担っていて、
3大栄養素のエネルギー
- 糖質:糖質1gから4kcalのエネルギーを作ってすぐに燃える
- タンパク質:タンパク質1gから4kcalのエネルギーを作って中々燃えない
- 脂質:脂質1gから9kcalのエネルギーを作ってじっくり燃える
という特徴を持っています。
では、ビタミンとミネラルは何の為に必要なのかというと、病気にならないように体の機能を調整したり3大栄養素の代謝を促す手助けをしています。
私たちは、主食として肉や魚などの食べ物を食べて栄養を摂取しますが、野菜には健康によい様々な成分や栄養素(緑黄色野菜にはビタミンAのようなβカロテンという成分、淡色野菜にはカルシウムやカリウムなどのミネラル)が多く含まれているので、目的に応じて主食に野菜を加えて5大栄養素をバランスよく摂取し、ビタミンやミネラルが不足しない食事を心がけてください。
※厚生労働省では、野菜は1日350g以上摂取するように定めています。
栄養成分については小学生の家庭科の時間に勉強したと思いますがもう一度おさらいしてみましょう。
2.3大栄養素の役割
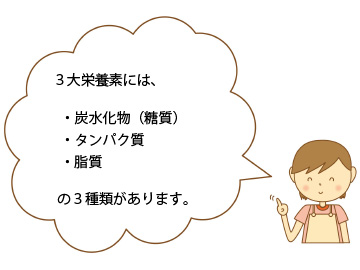
炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質は3大栄養素といわれており、直接エネルギーを作りだすことができ、体を動かすエネルギーとして使われる重要な栄養素です。
人間が健康に生きていく為には、次に示す3種類の栄養素が必要になるので意識しながら食事をしましょう。
炭水化物(糖質)
炭水化物とは、糖質と食物繊維を一緒にして表した3大栄養素の1つのことです。
糖質はエネルギーになる源として体に必要な栄養素で、体への吸収が早いのが特徴です。
※糖質1gから4kcalのエネルギーを作り出します。
糖質を食べるとブドウ糖に分解され体内に吸収しエネルギーとなり、糖質を摂りすぎて体内で余った場合は、脂肪に変わり体に貯蔵されます。
※糖質を消化する酵素はアミラーゼが有名です。
脳のエネルギーは糖質からのみ発生するので、炭水化物(糖質)ダイエットをして摂取量を極端に減らしている方は注意してください。
炭水化物(食物繊維)
食物繊維は人間の体内で消化されない成分です。
食物繊維の種類としては、水溶性食物繊維といって水に溶けるものと不溶性食物繊維といって水に溶けないものがあります。水に溶ける食物繊維は血糖値やコレステロール値を正常にする働き、水に溶けない食物繊維は腸の働きを助ける効果があります。
タンパク質
タンパク質は3大栄養素の1つです。主に筋肉、血液、皮膚、骨、髪の毛など体を作る為に必要な栄養素です。
※タンパク質1gから4kcalのエネルギーを作り出します。
タンパク質を食べるとアミノ酸に分解され体内に吸収し、再び再合成してタンパク質になります。
※タンパク質を消化する酵素はプロテアーゼが有名です。
過剰に摂取したタンパク質は一時的には貯蔵することはできますが、ほとんどは体外へ排出されてしまうので必要な量摂るようにしましょう。
※60kgの体重の人では60gくらいが摂取量の目安です。
脂質
脂質は3大栄養素の1つです。主に体の細胞膜やホルモンの材料、体温の維持に必要な栄養素です。
※脂質1gから9kcalのエネルギーを作り出します。
脂質を食べると脂肪酸に分解され体内に吸収されます。脂質を消化する酵素はリパーゼが有名です。
脂質は高エネルギーなので過剰に摂取した脂質は体内に貯蔵されてしまうので摂りすぎに気を付けてください。
また、オメガ3(DHA、EPA、アルファリノレン酸)とオメガ6(リノール酸、ガンマリノレン酸、アラキドン酸)の脂肪酸は体内で作ることができないので積極的に摂取するようにしましょう。
3.ビタミンの役割
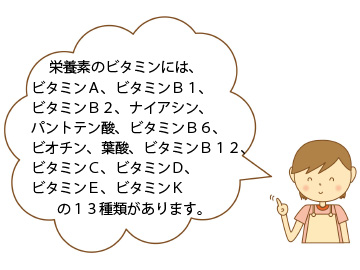
ビタミンはエネルギーを直接作りだすことはできませんが、体の機能を整える役割を持っている重要な栄養素です。
人間が健康に生きていく為には、次に示す13種類のビタミンが必要になるので意識しながら食事をしましょう。
ビタミンA
ビタミンAは脂溶性のビタミンで、目や皮膚の健康や粘膜の生成を助ける働きがあります。
みなさんは、βカロテンという言葉はご存じですか。βカロテンはカロテノイドの一種で、体内で必要な分だけβカロテンをビタミンAに変換して皮膚や粘膜を正常に保つ働きをしています。
※加熱することで吸収が促進されます。
また、ビタミンAに変換されなかったβカロテンは抗酸化物質として細胞の老化防止に役立ちます。
ビタミンAが不足すると視力が低下したり肌荒れが起きやすくなります。
ビタミンB1
ビタミンB1は水溶性のビタミンで、糖質を分解してエネルギーに変換する酵素の働きを助けます。
ビタミンB1が不足すると疲労感が現れるようになります。
ビタミンB2
ビタミンB2は水溶性のビタミンで、脂質をエネルギーに変換し栄養素の代謝を助ける働きをします。
ビタミンB2が不足すると口内炎が起こりやすくなります。
ナイアシン(ビタミンB3)
ナイアシンは水溶性のビタミンで、糖質、タンパク質、脂質がエネルギーになるのを助ける働きをします。
パントテン酸(ビタミンB5)
パントテン酸は水溶性のビタミンで、糖質、タンパク質、脂質がエネルギーになるのを助ける働きをします。
ビタミンB6
ビタミンB6は水溶性のビタミンで、タンパク質の代謝に大きく関わりがあり、皮膚や粘膜の健康を維持する働きをします。
ビタミンB6が不足すると肌荒れが起きやすくなります。
ビオチン(ビタミンB7)
ビオチンは水溶性のビタミンで、皮膚、目、髪の毛の健康を維持します。
ビオチンが不足すると、皮膚炎、脱毛、白髪などが起こりやすくなります。
葉酸(ビタミンM)
葉酸は水溶性のビタミンで、細胞を再生したり、赤血球中のヘモグロビンを作りだすサポートをしています。
熱に弱いので調理する時は気をつけてください。
葉酸が不足すると貧血になりやすくなります。
ビタミンB12
ビタミンB12は水溶性のビタミンで、赤血球中のヘモグロビンを作りだすサポートをしています。
ビタミンB12が不足すると貧血になりやすくなります。
ビタミンC
ビタミンCは水溶性のビタミンで、活性酸素を減らし細胞の老化防止をする抗酸化作用の働きが有名です。
その他には、コラーゲンの合成を助ける効果、メラニン色素を抑えてシミを防ぐ美肌効果などがあります。
ビタミンCが不足すると肌荒れになりやすくなります。
ビタミンD
ビタミンDは脂溶性のビタミンで、カルシウムの吸収を促し、丈夫な骨や歯を作る働きをします。
※日光に当たると微量ですがビタミンDが作られます。
ビタミンDが不足すると骨粗鬆症になりやすくなります。
ビタミンE
ビタミンEは脂溶性のビタミンで、細胞や脂質の酸化を防ぐ作用があり、血液をサラサラにして流れをよくしたり、肌の老化予防に役立ちます。
ビタミンEが不足すると腰痛や肩こりが起こりやすくなります。
ビタミンK
ビタミンKは脂溶性のビタミンで、骨を健康に保ったり、ケガで出血した時に血を固めて出血を止める働きをします。
ビタミンKが不足すると出血した血が中々固まらなくなります。
4.ミネラルの役割
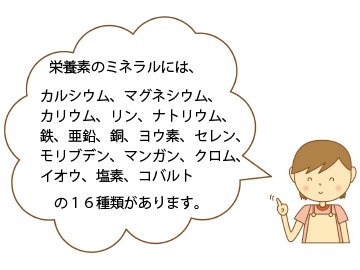
ミネラルはエネルギーを直接作りだすことはできませんが、骨や歯を作ったり体の機能を整える役割を持っている重要な栄養素です。
人間が健康に生きていく為には、次に示す16種類のミネラルが必要になるので意識しながら食事をしましょう。
カルシウム(Ca)
カルシウムは主要元素で、骨や歯を作り強くする働きをするミネラルです。
※骨や歯は、70%のミネラル(カルシウム、マグネシウム、リンなど)と30%のコラーゲンでできています。
その他では、筋肉の動きを良くする、精神状態を安定させる、ケガをした時の出血を早く止めたりする効果があります。
骨粗しょう症予防、運動をよくする人、毎日イライラしている人はカルシウムを積極的に摂るように心がけましょう。
※摂り過ぎると、マグネシウム、鉄、亜鉛の吸収が悪くなるので気をつけましょう。
マグネシウム(Mg)
マグネシウムは主要元素で、糖質、タンパク質、脂質をエネルギーに変えたり、筋肉や神経などの体の組織を作る酵素の働きを助けるミネラルです。
また、マグネシウムは骨や歯を作る成分でもあり、カルシウムが骨や歯から溶け出しにくくしたり便秘解消の効果もあります。
カリウム(K)
カリウムは主要元素で、体内の水分とナトリウムの割合を一定に調節して、過剰に摂取したナトリウムを排泄する働きがあるミネラルです。
カリウムを摂ることによって、体内の塩分濃度を下げて高血圧予防やカルシウムの排出を抑えるので骨を強くする効果があります。
リン(P)
リンは主要元素で、カルシウム・マグネシウムとともに骨や歯を作る成分です。
主に、ハムやソーセージなどの加工食品の添加物としてに多く使われているので摂取しやすいミネラルです。
但し、リンを摂り過ぎるとカルシウムが減少して骨が弱くなってしまうので気をつけましょう。
ナトリウム(Na)
ナトリウムは主要元素で、体内の水分とカリウムの割合を一定に保ちながらpHや水分量を調節するミネラルです。
ナトリウムを摂り過ぎると血液量が増えて高血圧になるので気をつけましょう。
鉄(Fe)
鉄は微量元素で、酸素を体の細胞へ運ぶ働きをします。
鉄が不足すると貧血になりやすくなります。
亜鉛(Zn)
亜鉛は微量元素で、体を健康に維持する為に必要なミネラルです。
亜鉛が不足すると味覚障害が起こることがあります。
銅(Cu)
銅は微量元素で、鉄が体に吸収されるようにサポートしています。
ヨウ素(I)
ヨウ素は微量元素で、甲状腺ホルモンに関係したミネラルです。
セレン(Se)
セレンは微量元素で、抗酸化作用がある酵素なので免疫力を強くする働きをして老化予防に効果があります。
モリブデン(Mo)
モリブデンは微量元素で、尿素を作ったり、食品添加物などの毒を解毒したり、血糖値の上昇を抑える働きがあります。
マンガン(Mn)
マンガンは微量元素で、糖質や脂質の代謝に大きく関わりがあり、生殖機能を維持する働きをします。
クロム(Cr)
クロムは微量元素で、血糖値の上昇を抑える働きをします。
イオウ(S)
イオウはタンパク質(ケラチン)やアミノ酸(シスチンなど)の成分として必要なものです。
塩素(Cl)
塩素は、NaClとしてナトリウムと結合した状態で摂り入れられます。胃酸を作ったりタンパク質の消化酵素のペプシンの働きをサポートしています。
コバルト(Co)
コバルトはビタミンB12の構成成分として体内に存在しています。
(記事作成日:2017年8月7日、最終更新日:2019年8月15日)


